こんにちは、白々さじきです!
今回は、Findyが2025年2月25日に実施した「QAエンジニア特集」イベント に参加し、「弥生株式会社」「千株式会社」「株式会社タイミー」 の3社がどのようにQA(品質保証)に取り組んでいるのか、実際のQAエンジニアの事例をもとにまとめました!
各社で異なるアプローチを取りつつも、共通しているQAの考え方 もありましたので、まずはそこから解説していきます!
1. そもそもQA(品質保証)とは?
QA(品質保証)というと、「テスト専門の部署」「不具合を見つける仕事」というイメージを持たれがちですが、本来のQAは単にバグを見つけるだけではありません!
QAの目的は、以下の3つに集約されます
- プロダクトの価値向上(品質リスクの分析・改善提案)
- 開発プロセスの継続的な改善(仕様変更の影響管理・テスト自動化)
- ユーザー体験(UX)の最適化(カスタマーサポートとの連携・フィードバック収集)
「開発前・開発中・リリース後までQAが関与することが理想的な品質保証」とされています。
2. 3社に共通するQAの取り組み
今回の3社(弥生・千・タイミー)では、以下の3つのポイントが共通していました
① 上流工程からのQA関与
- 要件定義や設計レビューの段階からQAエンジニアが参加
- 設計の抜け漏れ・仕様のあいまいさを早期に発見する
- 「リリース直前の手戻り」を防ぐことで、開発効率を向上!
② 自動テストの推進
- 結合テストやリグレッションテストはできる限り自動化
- QAが人間の目で確認すべきテスト(探索的テスト)にリソースを集中!
- GitHub ActionsやCI/CDパイプラインを活用し、テストを継続的に実施
③ カスタマーサポート(CS)との連携
- ユーザーの問い合わせ内容をQA・開発チームへフィードバック
- 「本当に必要とされている品質」 を分析し、優先度を決める
- リリース後も定期的に「後追いテスト」を行い、品質を改善
3. 各社の特徴的なQAの取り組み
では、それぞれの会社でどのような 「個別の取り組み」 をしているのか、詳しく見ていきます!
3.1. 弥生株式会社 – 法令対応&業務品質を支えるQA
✅ 特徴
- 法令遵守を最優先にした品質保証(会計・税務ソフトの特性上必須)
- 静的テスト(設計レビュー)を徹底 し、要件の抜け漏れを防ぐ
- 探索的テスト を活用し、ユーザーの実際の操作をシミュレート
✅ 具体的な取り組み
- 設計段階のレビューをQAがリード(「仕様が適切か?」を徹底確認)
- 法律改正や税制変更に対する影響調査
- ユーザーの誤操作を想定したテスト(ブラックボックステスト)を実施
3.2. 千株式会社 – 多様なユーザーに対応するQA
✅ 特徴
- 保育園・幼稚園の先生&保護者という「異なるユーザー層」を考慮したQA
- 大規模な写真データ(6.3億枚!)を扱うシステムの品質保証
- 「すべてをテストするのではなく、優先度をつけてテストする」戦略
✅ 具体的な取り組み
- 「バグ(リリース後の不具合)」と「手戻り(開発中の修正)」を明確に区別
- テストの優先順位を決め、「本当に必要なテスト」にリソースを集中
- リリース後も後追いテストを行い、実際のユーザー行動を分析
3.3. 株式会社タイミー – QAの組織文化を強化
✅ 特徴
- QAコーチとSET(Software Engineer in Test)の2軸体制
- QAのスキルを組織全体に広げる「QAコーチ」の存在
- Critical User Journey(CUJ)をベースにした品質基準策定
✅ 具体的な取り組み
- QAコーチがワークショップを開催し、QAスキルを社内に展開
- SETがCI/CD環境を整備し、継続的インテグレーションを強化
- CUJ(Critical User Journey)を軸に、ユーザーが最も使う機能を優先的にテスト
4. まとめ:QAの未来は「開発と一体化」
今回の3社の事例から見えてきたのは、QAは単なる「テスト実施者」ではなく、プロダクトの品質を守る戦略的な役割を担っている ということです!
特に「QAの組織文化醸成」 といった考え方が共通しており、開発とQAの壁をなくし、一体化することが求められています!
今後も、QAの役割は 「開発スピードと品質の両立」を支える重要なポジション であり続けると思いました!
今回の内容を参考に、自社のQAプロセスを改善してみてくださいね!
サポートのお願い
下記リンクからお買い物いただけると、ブログ運営のための費用が増え、有料サービスを利用した記事作成が可能になります。ご協力よろしくお願いします!

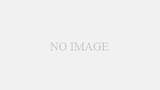
コメント